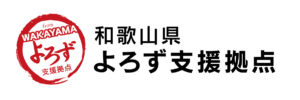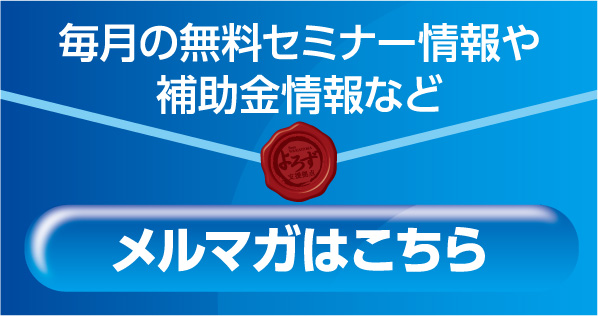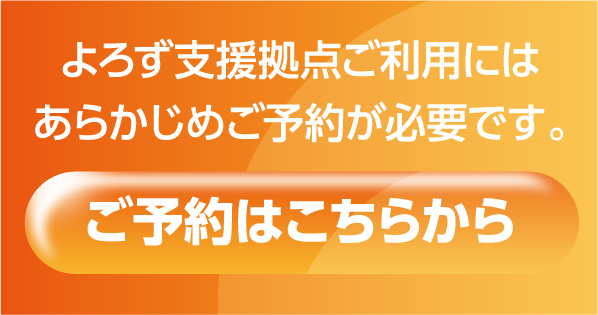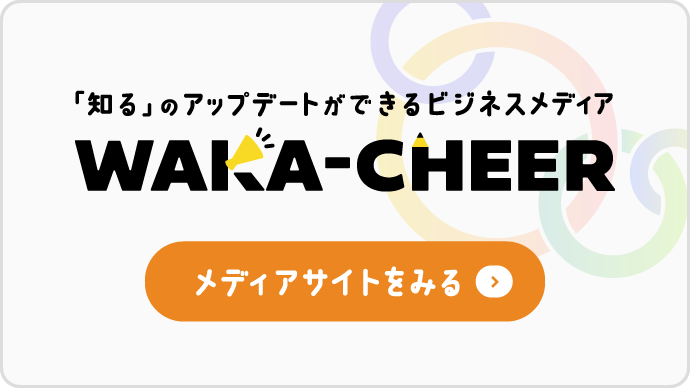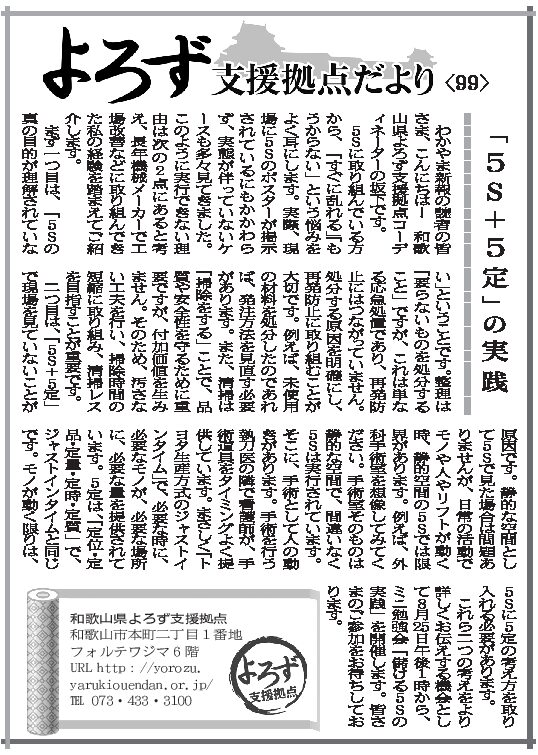
わかやま新報の読者の皆さま、こんにちは! 和歌山県よろず支援拠点コーディネーターの坂下です。
5Sに取り組んでいる方から、「すぐに乱れる」「もうからない」という悩みをよく耳にします。実際、現場に5Sのポスターが掲示されているにもかかわらず、実態が伴っていないケースも多々見てきました。このように実行できない理由は次の2点にあると考え、長年機械メーカーで工場改善などに取り組んできた私の経験を踏まえてご紹介します。
まず一つ目は、「5Sの真の目的が理解されていない」ということです。整理は「要らないものを処分すること」ですが、これは単なる応急処置であり、再発防止にはつながっていません。処分する原因を明確にし、再発防止に取り組むことが大切です。例えば、未使用の材料を処分したのであれば、発注方法を見直す必要があります。また、清掃は「掃除をする」ことで、品質や安全性を守るために重要ですが、付加価値を生みません。そのため、汚さない工夫を行い、掃除時間の短縮に取り組み、清掃レスを目指すことが重要です。
二つ目は、「5S+5定」で現場を見ていないことが原因です。静的な空間として5Sで見た場合は問題ありませんが、日常の活動でモノや人やリフトが動く時、静的空間の5Sでは限界があります。例えば、外科手術室を想像してみてください。手術室そのものは静的な空間で、間違いなく5Sは実行されています。そこに、手術として人の動きがあります。手術を行う執刀医の隣で看護師が、手術道具をタイミングよく提供しています。まさしく「トヨタ生産方式のジャストインタイム」で、必要な時に、必要なモノが、必要な場所に、必要な量を提供されています。5定は、「定位・定品・定量・定時・定質」で、ジャストインタイムと同じです。モノが動く限りは、5Sに5定の考え方を取り入れる必要があります。
これら二つの考えをより詳しくお伝えする機会として8月25日午後1時から、ミニ勉強会「儲ける5Sの実践」を開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。