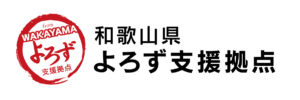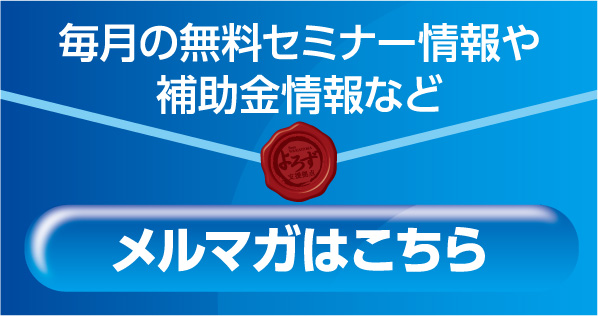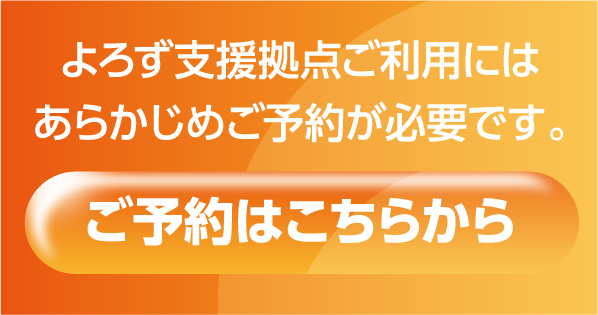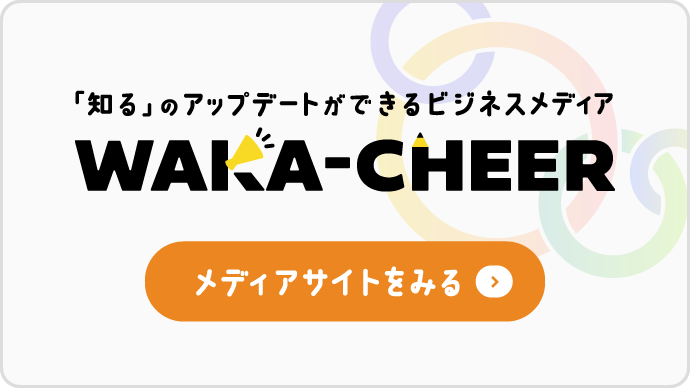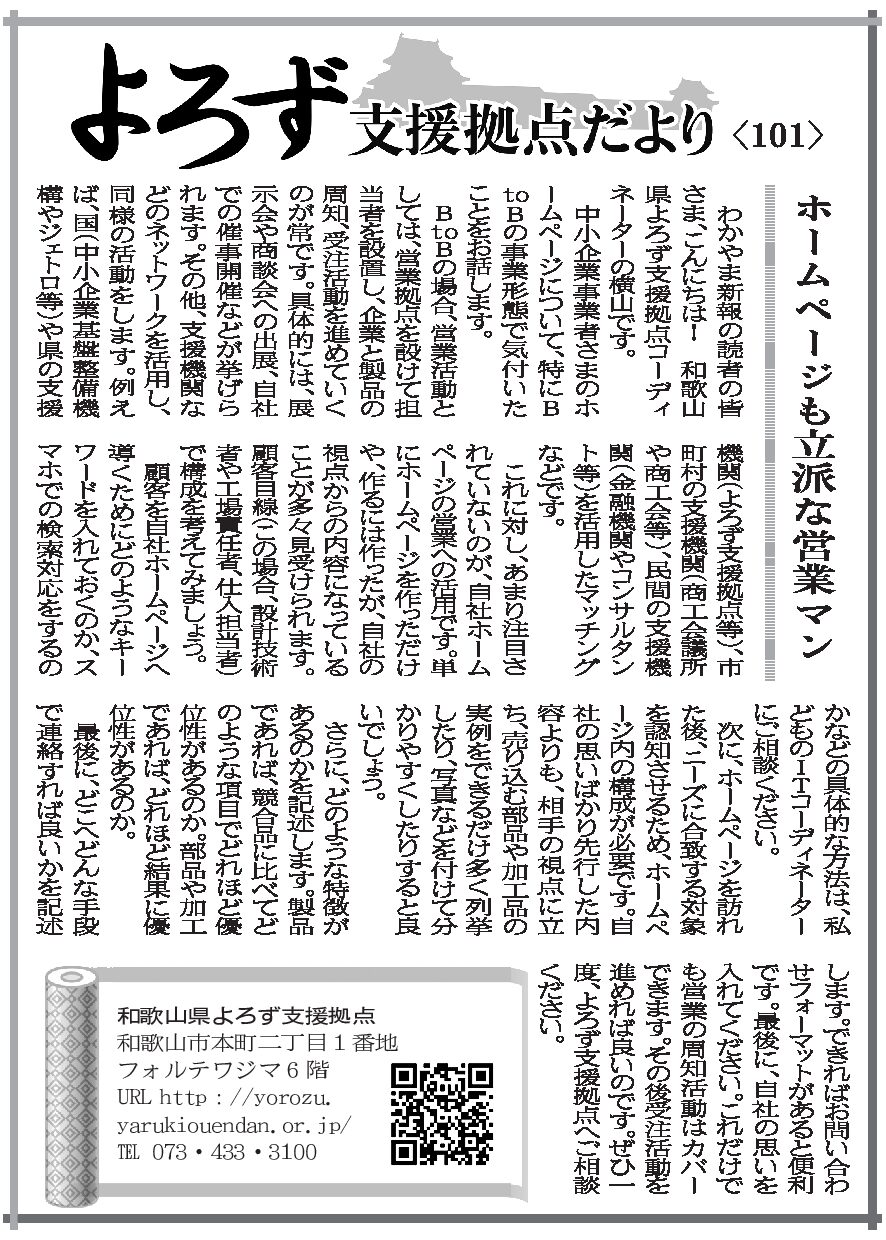
わかやま新報の読者の皆さま、こんにちは! 和歌山県よろず支援拠点コーディネーターの横山です。中小企業事業者さまのホームページについて、特にBtoB の事業形態で気付いたことをお話します。
BtoBの場合、営業活動としては、営業拠点を設けて担当者を設置し、企業と製品の周知、受注活動を進めていくのが常です。具体的には、展示会や商談会への出展、自社での催事開催などが挙げられます。その他、支援機関などのネットワークを活用し、同様の活動をします。例えば、国(中小企業基盤整備機構やジェトロ等)や県の支援機関(よろず支援拠点等)、市町村の支援機関(商工会議所や商工会等)、民間の支援機関(金融機関やコンサルタント等)を活用したマッチングなどです。
これに対し、あまり注目されていないのが、自社ホームページの営業への活用です。単にホームページを作っただけや、作るには作ったが、自社の視点からの内容になっていることが多々見受けられます。顧客目線(この場合、設計技術者や工場責任者、仕入担当者)で構成を考えてみましょう。
顧客を自社ホームページへ導くためにどのようなキーワードを入れておくのか、スマホでの検索対応をするのかなどの具体的な方法は、私どものITコーディネーターにご相談ください。
次に、ホームページを訪れた後、ニーズに合致する対象を認知させるため、ホームページ内の構成が必要です。自社の思いばかり先行した内容よりも、相手の視点に立ち、売り込む部品や加工品の実例をできるだけ多く列挙したり、写真などを付けて分かりやすくしたりすると良いでしょう。
さらに、どのような特徴があるのかを記述します。製品であれば、競合品に比べてどのような項目でどれほど優位性があるのか。部品や加工であれば、どれほど結果に優位性があるのか。
最後に、どこへどんな手段で連絡すれば良いかを記述します。できればお問い合わせフォーマットがあると便利です。最後に、自社の思いを入れてください。これだけでも営業の周知活動はカバーできます。その後受注活動を進めれば良いのです。ぜひ一度、よろず支援拠点へご相談ください。